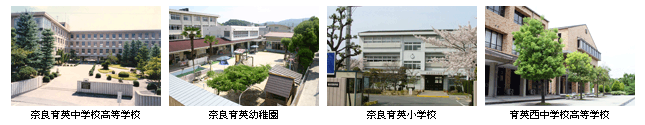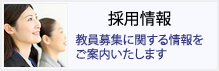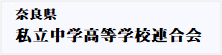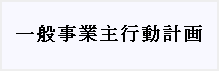創立100周年
創立100周年に向けて
奈良育英学園は、1916年(大正5年)藤井高蔵、ショウ夫妻が「私立育英女学校」を創立して以来、幼稚園から高校までを擁する、県内有数の私学として歩んでまいりました。今や3万人にも及ぶ本学園の卒業生が、日本のみならず世界中で活躍するに至っております。
この長きにわたる伝統のうえに、来たる2016年には、いよいよ本学園創立100周年を迎えます。私たちは、今まで多くの方々より賜りましたご厚情を心から感謝しつつ、創立当初の熱い思いを心に蘇らせ、新たな気持ちでその時を迎える決意です。
この大きな節目を迎えるにあたって、私たちは、学園建学の精神である「完全なる人格の育成」という理念を継承するとともに、時宜に応じた清新な教育活動の創造にも一層情熱を傾注し、一意専心、今を生き抜く私学としての学風をさらに強固に築くべく、鋭意努めてまいります。
つきましては、創立100周年に先立つこの時期に、更なる学園発展に向けての具体的な目標を設定し、ここに「奈良育英ビジョン」として、その達成に邁進していくことをお約束いたします。広く皆様方のご理解とご鞭撻をお願い申し上げる次第です。
2012年6月吉日
学校法人 奈良育英学園
理事長 藤井 宣夫
5つの基本目標
- 独自の教育理念に基づく魅力ある私学教育の実現
- 学園経営基板の強化
- 系列各校園の連携強化
- 教職員の教育力向上
- 教育環境の整備・充実
わが学園の使命 藤井長治
そもそも、私学は一私人の創意と責任において創立され、そうして経営されます。すなわち、教育について特別の識見と高遠の理想をいだく人が、私財を投じ、情熱を傾けてこれを創立し、そしてこれに共鳴する多くの人々の精神的、物質的協力を基礎として、段々成長し、発展するのが私学の姿であります。
したがってそこには、創立者の人格と理想とを核心とした、独特の精神と魂とがあって、物質的な設備はむしろ後からこれに従って行くのが常であります。わが学園が現状にまで発展して来たのは、各方面の方々の大きな御協力の賜であることは勿論でありますが、わが学園が創立の当初より、このような私学の良い本質を持ち、又創立者の先生たちがその本質を育て伸ばすことに努力してきたことが、大きな要素であると信じます。
私は創立者の両先生が、わが学園をしてこうした私学の本当の進むべき道に歩ませて下さったことを何にもまして感謝しています。両先生によってうちたてられた建学の精神は、要約すると、
神を信じ人を愛し、道義を重んじ真理を愛し、職分を貴び
勤労を楽しむ精神を涵養し、完全なる人格を育成する
ということになります。われわれは創立四十周年を機に、この建学の精神を一層明らかにすることにより、私学としての使命を十分果たしたいと思います。私学経営には幾多の困難があります。しかし私学教育の負わされている使命は重いのであります。われわれここに与るものは、その使命の的確な認識と、限りない誇りをもって、この道を進むものであります。
遠い道であろうし、けわしい道であるかも知れません。ただ、神の恩ちょうと共鳴者の協力を信じて、いかなる時も希望を失わず、この道を進んで行く覚悟であります。
奈良育英学園 創立物語
- 「私立育英女学校」創立
-
「この学校を女学校としてやっていけないでしょうか」。
女子師範学校の予備校ではなく、あくまで普通教育の女学校をつくる。ショウのこの考えに、最初は慎重な姿勢を見せていた高蔵も、次第にその熱意に動かされ、最後にはこう言ったのです。「それは意義のある事業だ。よし、共にやろう」。
大正五年早春、第一次世界大戦に日本が参戦して一年余りが経った頃のことでした。共に敬虔なキリスト教徒であった夫妻は、当時関係の深かった日本聖公会奈良基督教会の吉村大次郎牧師より、当教会を母体とする「奈良育英学校」の処遇をめぐって相談を受けることになりました。
「奈良育英学校」は、奈良基督教会創建の功労者である玉置格氏によって、明治三十九年に女子師範学校の予備校として設立され、県教育界に対する一定の役割を果たしていました。しかし大正三年頃、県内で女子師範学校廃止の機運が高まった影響を受け、またたく間に生徒が激減、ついには廃校に追い込まれていったのです。
学校は創建時の教会敷地にあり、建物も旧教会堂が使われていました。この由緒ある場所を放置するのに忍びない思いを抱く吉村牧師は、当時県議会議員に当選したばかりの藤井高蔵に、その利用についての相談を持ちかけたのでした。この話に対して積極的に身を乗り出したのは、むしろ妻のショウの方でした。法律家を志し、後にジャーナリストから地方政治家の道を歩み始めていた高蔵に対し、ショウはもとより教職を志し、すでに郷里の大分高等女学校や、すでに廃校になった奈良高等女学校などの教師も経験しており、とりわけ女子教育に対する情熱は並々ならぬものがあったのです。
夫婦の決意は固まりました。学校名は「私立育英女学校」。後日設立の書類を整え、ショウは奈良市の五井寿愷助役を訪ねました。しかし、県知事への取り次ぎを願い出たショウに、五井助役は手厳しい忠告を与えます。「止めておきなさい。公立の女学校さえ経営に苦労しているというのに、どうせ困難な目にあうにきまっている」。それは確かに、当時の厳しい県内情勢に立脚した、説得力のある言葉でした。これですっかり意気消沈して帰宅したショウを、今度は高蔵が叱り、励ましたのでした。
「そのくらいのことでへこたれていてどうする。厳しいことは、こうと決めた時から分かっていたことではないのか。たとえ一人でもよい。一緒に良き妻、良き母を育てることを本望とすべきだ。だからもう一度、五井さんに頼んできなさい」。
この言葉が、ショウを大いに奮い立たせたことは言うまでもありません。
1916(大正5)年四月十七日、藤井高蔵、ショウ夫妻によって、奈良市花芝町に創設された「私立育英女学校」から、奈良育英学園百年の歴史が始まります。その年迎えた女生徒の数、十七名。ささやかな、しかし人格教育の場としての確かなスタートでした。

- 「奈良育英高等女学校」の新設
-
その後「私立育英女学校」は、順調に生徒の数を増やしていきました。しかしそれとともに、校舎の狭さや設備の不十分さも一層目立つようになりました。
もともと設備の面で高等女学校の認可を受けられず、各種学校の扱いでスタートした学校でした。それでも、教職の場で積み重ねられたショウの経験を活かして、私塾のような手厚い教育が行われていました。しかし、かねてからの目的を達成するためには、さらにもう一段階の飛躍が必要でした。夫の高蔵も、次第に学校経営者として、そして教育者としての自覚を高め、大正六年に県政界から退いた後は、教育の世界に身を投じる覚悟を固めていったのです。
「なんとしても高等女学校をつくろう」。
高蔵とショウの思いはこの一点に向けられました。当時は志願者に対してあまりに学校が少なく、進学をあきらめる女生徒が多いことも、ショウの心を痛め続けていたのでした。しかし、高等女学校を設立するためには、それにふさわしい土地と建物等の設備が必要です。そして言うまでもなく、そのためには多くの資金が必要になってきます。
大正九年二月、校長に就任した高蔵は、女子教育の重要性を情熱的に訴えた「私立育英女学校建築費寄附金募集趣意書」を起草し、高等女学校設立にむけての活動を開始します。この賛同者には木田川奎彦奈良県知事を始め、国会議員や実業家、学者、宗教・教育関係者など、各界のそうそうたる有力者が顔をそろえ、これに力を得て、高蔵は資金獲得のために東奔西走の日々を送るようになります。奈良市周辺、県北部はもとより、西吉野出身である高蔵には、県南部からも篤い応援が寄せられることになりました。
この結果、県内外の二百五十名にも及ぶ人々から、当時の金額にして合計二万五千円の寄附金が集まり、これに高蔵の自己資金を加えて、大正十一年十一月、奈良市郊外の法蓮の地に校地を買い求め、いよいよ校舎が建築される運びとなりました。
ところがこの時、京都で起きた銀行の取り付け騒ぎにより、校舎建築目前で資金が滞るという、思いもよらない事態に直面することになります。夫妻はあらゆる手段を講じて資金の調達に努力します。しかし、なかなかそれを充たすまでには至りません。翌十二年の二月には、文部省から設置の認可がおりたという「朗報」が届き、それが夫妻を焦らせ、ますます窮地に追いやります。
万策尽きたかと思われたその時、まさに天からとしか言えないような救いの手が差しのべられたのでした。製墨業の老舗「古梅園」を経営する松井貞太郎氏より、無利子貸付けの申し出があったのです。夫妻は互いに肩を抱き合い、嬉し涙に咽びました。それまでにあまり面識のなかった松井氏の、予想だにしなかったこの厚情が、いかに夫妻を驚かせ、歓喜に導き、そして勇気づけたかは想像に難くありません。後に高蔵は、「この恩だけは決して忘れるな」と重々妻に言い遺して、この世を去ったのでした。
こうして、多くの人々の篤い志に支えられ、夫妻の情熱は「奈良育英高等女学校」となって実を結び、大正十二年六月一日、法蓮の新校舎で授業がスタートしたのです。
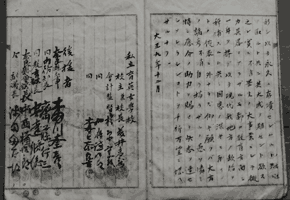
- 高蔵逝く
-
法蓮の地に新築された校舎は、「実にモダンな建物だった」とショウ自身が述懐し、また当時の教員が、「チョコレート色の木の中に窓枠だけが白い、実に気持ちの良い校舎でした」と表現したように、女学校にふさわしい清新な建物でした。ただ当時の法蓮は、添上郡から奈良市に編入したばかりで、校舎は田畑が広がる中にぽつんと建っているような状態でした。水道もまだ通っていなかったので、年老いた用務員が毎朝近所の井戸まで水を汲みに出かけ、学校では水を極めて大切に使ったといいます。
資金の事情によって校舎建築が遅れたため、この地で授業が始まったのは大正十二年の六月になってからでした。しかも高等女学校はあくまで新設で、従来の「私立育英女学校」は「奈良女子高等裁縫学校」として続けられることになり、寄宿舎などすべてが花芝町から法蓮の地に移るには、まだしばらくの時間を必要としました。
高等女学校の開校式がその年の十二月一日になったのは、そういった事情に加えて、夫妻や家族の健康の問題もあったようです。この間の想像を超えた苦労は、夫妻の心身に大きな負担を強いたばかりでなく、家族全員にも多大な影響を与えたのでした。
六月に三男が重病となり入院、そしてその看病に追われたショウ自身も入院せざるを得ない事態となり、ついに七月二十日、ショウは三男の遺骨を抱いて退院することになってしまったのです。多忙のために息子を死まで追いやったことに対する、ショウの精神的な打撃はもちろん、三男をことのほか愛していた高蔵の悲嘆もまことに大きいものがありました。高等女学校設立に奔走し、その後も心身をすり減らす日々を送っていた高蔵に、三男の死はきわめて大きな打撃を与えたのです。
夏が過ぎ、実りの秋が来ました。人々が食欲を回復する頃、高蔵はそれに反して食事が進まなくなりました。歩くのにもすぐに疲労を訴えるようになり、そして高等女学校の開校式を迎える十二月、衰えは誰の目にも明らかとなりました。その後京都帝大病院で診察のうえ、翌年二月二日に手術。しかし、胃癌はすでに手遅れの状態でした。
退院後、いったん元気を取り戻したかに見えた高蔵でしたが、病魔の進行がもはや取り返しのつかないものであることを、やがて自らも気付くことになります。高等女学校の第一回卒業式は、高蔵にとっては最後の卒業式になりました。
「人は誠をもって世に立つべきである。・・・・・至誠は力である。偉い人になるよりも、先ず誠の人となれ・・・・・」。懇々と諭す高蔵の目には、うっすらと涙が宿っていました。
その後四月十日に挙行された入学式が、心血を注いできた学校との最後の別れになりました。日を追うごとに病状は悪化し、ついに大正十三年六月九日、高蔵はこの世を去ったのです。享年四十五歳。あまりにも早すぎる創立者の死でした。
ショウへの遺書には、「無念だがこれも天命なので仕方がない。家族や学校の将来についてはすべてショウに託す」といった旨が、妻への感謝の言葉とともに綴られていました。「自らの保険金を学校の建築費用に充てよ」という言葉まで遺されていました。
悲しみにふける間もなく、夫の遺言を受けたショウの苦闘が始まります。


- ショウの苦闘
-
高蔵の死後、ショウは自分がすぐさま学校を継ぐべきか、大いに悩みます。当時は学校の顧問として、松井貞太郎氏を始め、高等女子師範(現奈良女子大)や県女子師範(現奈良教育大)、そして奈良中学(現奈良高校)の各校長が名を連ねていました。これらの人々が集って協議した結果、やはり学校を継ぐのはショウが最もふさわしいとの結論になりました。
しかしショウにとって、家庭を持つ女性の身が学校の経営と校長とを兼ねることは、あまりにも負担のかかることでした。経営は高蔵の遺言を守って引き継ぐとしても、校長の重い立場を兼務することは厳しい、というのがショウの率直な思いでした。
このショウの気持ちを尊重して校長の人選が進められることになりました。しかし、それは難航をきわめることになりました。いまだ官尊民卑や男尊女卑の風潮が根強い当時の社会にあって、行く末も定かでない私立の女学校の校長を、あえて引き受けようとする者はなかなかいなかったのです。それならもはや学校と運命を共にしよう、とショウが決死の覚悟で校長も引き受けようとした矢先、やっと適任者が現れました。長年女高師付属女学校の勅任教諭を務めていた、永沢定一氏が校長として紹介されたのでした。
この間、ショウのもとには「学校のようなものを妻が継ぐべきものではない」といった中傷めいた発言が伝わったり、「学校を捨てるか子供を捨てるか、そのいずれかを選ぶべきだ」といった忠告をする人が現れたりしました。しかしショウはあくまで自分の考えを貫き、高蔵の遺言を守って進もうとしたのでした。むしろこの経験は彼女を、少々のことでけなされたり褒められたりしても、決して動じない人間にしていったのです。
幸いにも永沢氏が校長に就くことにより、ショウは経営者としての仕事に専念することができました。高蔵の遺言どおりに、生命保険金をなげうって建築費用を捻出したり、佐保小学校や郡山中学など、公立学校の旧校舎の払い下げを積極的に受けたりして、精力的に校舎や教室の整備拡充に努めます。永沢氏に代わって校長に就くことになった昭和三年には、競売にかけられた大阪曽根崎小学校の講堂を購入し、講堂建設の念願を果たします。
ショウはこういった購入方法を卑下するどころか、「まだまだこんなに使えるものを粗末にしている。それを役人に見せてやるのだ」と誇りにさえしていたといいます。そしてこのショウの努力を支えたのが、宮大工の大木吉太郎氏でした。大木氏は奈良基督教会の和風教会建築などを手がけ、今もその名を語り継がれる名工です。新築ばかりでなく、払い下げを受けた古い建物も、大木氏は次々に蘇らせ、立派な姿に変えていったのです。後に氏は、「育英の建築と私の生涯は不離一体」とまで述べています。氏をここまで思わせるに至ったのも、ショウのひたむきな生き方と、思いやりに満ちた人柄ゆえだったのでしょう。
学校の充実に対するショウの情熱は、卒業生や保護者の気持ちも駆り立てずにはいませんでした。備品購入の費用を捻出するためにショウが発案したバザーは、多くの篤い支援を受けて大々的に催されるようになり、昭和三十年頃まで続けられることになります。
高蔵の死から、早くも十年の歳月が流れようとしていました。昭和七年には、教育功労者として特別拝謁の栄にも浴し、ショウは教育者として確かな地位を築いたのです。



- 深い苦悩のうえの飛躍、そして夫のもとへ
-
周囲の篤い支援にも支えられて、ショウの学校経営は順調に進みました。
しかし、高蔵の死後十年が経とうとする昭和八年頃、ショウにとって最大の精神的危機が訪れます。経営に携わろうとした十年前の不安や疑問が再び頭をもたげ、一層強く彼女を苦しめるようになったのです。経営者として、そして教育者としての資質に対する疑問、母としての役割を充分に果たせていないことへの負い目などが、声ならぬ声となって彼女を大いに苦しめました。学校を立派な誰かに手渡して、自分は淋しい子供たちの真の母となるべきではないか・・・。昭和九年の春から夏にかけての半年間は、最もショウを苦しめた時期でもありました。
この深い苦悩から彼女を救ったのは、やはり信仰の力でした。当時相談相手であったキリスト教信者服部治氏の温かい助言もあり、ショウはひたすら祈り続けました。
そして、大きな転機が訪れます。「悩んでいた自分は結局思い上がった自分に他ならないのだ。この間違った精神をいったん神にお返しし、そして再びこの学校を、神からの授かりものとしてお受けしよう」。この思いによって、ショウはすっかり生まれ変わったのです。
昭和十一年、学園は創立二十周年を迎えました。十一月一日に挙行された記念式典は、あたかも生まれ変わったショウと学園の姿を象徴するかのようでした。一戸二郎奈良県知事、山本米三貴族院議員、そして鳩山春子全国女子職業学校長協会代表理事など、そうそうたる顔ぶれが来賓として祝辞を述べました。参列者も各界の名士が顔を並べ、誰もが高蔵の遺志を継いで奮闘する、ショウと学園の発展を祝ったのです。
ところがこの頃、奈良市立高等女学校の設立運動が起こり、「新築か育英買収か」という予期せぬ話が持ち上がりました。しかし自信をなくした数年前とは違い、もはやそのような話に易々と乗るショウではありません。この話から学園を守るには、何よりも設備の拡充が必要と判断したショウは、約四千五百坪の校地買収というとてつもない目標を立てました。そして驚くべきことに、その後数年でそれを実現してしまうのです。この結果、ほぼ現在の規模に匹敵する学園の敷地が確保されたのでした。昭和十六年には、公立学校も及ばないほどの、立派な体育館も完成しました。当時のショウの苦労ぶりは、「これが学園の全財産です」と財布を取り出して苦笑した、というエピソードからも窺われます。
しかしこの苦労が、結局はショウの健康を害することになります。しかも教育の現場では、昭和九年より精神的にショウを支えてきた三谷久男教頭の突然の転職、後継者として育てあげた長男隆一の召集など、ショウを寂しくさせる出来事も重なりました。
身体の不調を覚えつつも、このような状況の中で満足に診察を受けられないまま、結局ショウの体を蝕んだ癌は、かつての高蔵同様、すでに手遅れの状態になっていたのです。
太平洋戦争開戦後の昭和十七年三月四日、「お母さん、しっかりして」という家族の励ましに、「あなた方こそしっかりしなさい」と気丈に言い遺し、ショウは息をひきとりました。
翌七日、自ら苦労して建てた体育館で、ショウの学校葬が執り行われました。助言者であった原田美実氏の司式で全校生徒に見送られ、ショウは夫のもとに旅立ったのでした。



- 夫妻の遺業を引き継いで
-
ショウの逝去により、校長には長男の藤井隆一が就任しました。しかし、隆一は応召中であったので、奈良中学から転勤したばかりの山本長治(長女の婿)が、校長事務取扱いに就くことになりました。幸いこの年の十二月に隆一が召集解除となり、再度召集を受ける昭和二十年三月までの二年余りの間、校長として陣頭指揮を執ることになります。
隆一は京都帝大法学部を卒業後、学園の経営を継ぐべく、再び同大学の文学部で教育学を学びました。その闊達で明るい人柄により、リーダーとしての実行力を遺憾なく発揮して学園の経営にあたりました。昭和十八年には、大正期の「奈良女子高等裁縫学校」から続いてきた「奈良育英高等実践女学校」を廃止し、高等女学校の発展的な一元化を図ります。そして彼の最も大きい功績が、翌年に実行された学園の財団法人化です。このことは既に父高蔵が設立の趣意書で明言しており、母のショウも遂に果たせなかったことで、その遺志を継いだ隆一が、学園の近代化に向けた大きな課題として実現させたものです。
時は昭和十九年、太平洋戦争は激しさを増し、戦局は緊迫の度を加えました。七月には本学園にも学徒勤労動員の出勤命令が下り、奈良県内はもとより、愛知県にまで動員されることになったので、学校を挙げての出勤態勢が整えられました。
元来生徒も職員も汗水流してよく働き、学園の充実発展に身を捧げる美風が形づくられていました。運動場造成の際、生徒達は毎日黒髪山方面から土を運んでは整地をし、ほとんど自分達の手で立派に完成させたほどです。この動員において、皆必死で勤労に励んだことは言うまでもありません。その結果、関係者からの大きな信頼を得るまでになり、日頃生徒達が抱いていた官立学校へのコンプレックスを吹き飛ばすことにもなりました。
翌二十年三月には校長の隆一が再度召集を受けました。東京へ入隊する途上、隆一は愛知県安城町の勤労動員先に立ち寄り、その場で卒業式が行われました。学園の歴史上、唯一外部での、まさに涙の卒業式でしたが、ゆっくり感慨に浸る間もなく、翌晩には全員が駅まで入隊する校長の見送りをすることになります。しかし列車を待つ間に空襲の知らせがあり、全員大急ぎで工場に戻らなくてはなりませんでした。それは名古屋大空襲の夜で、隆一校長と迎えた最後の夜にもなったことを、誰も知る由がありませんでした。
七月末、戦局が増々切迫の度を強めた折、突如学園に悲報が舞い込みます。隆一校長の戦病死の知らせでした。胸膜炎の悪化により、終戦直前の七月三十日、千葉県の陸軍病院にて逝去。享年三十五歳。学園の未来を託された若きリーダーの、痛恨の死でした。両親の遺志を継ぎ、学園の発展を期していた隆一は、父同様、その途上で無念の死を遂げたのです。悲報を受けた学園は、深い悲しみに包まれました。
その後の八月十五日、終戦という未曾有の事態を迎え、学校葬が執り行われたのは同月十八日でした。リーダーを失ったまま、混沌たる戦後の状況に身を置いた学園は、まさしく大きな危機に直面していました。藤井高蔵、ショウ夫妻、そして隆一の命と共にある学園を、これから一体誰が引き継ぎ、その経営を担うのか。
この重責を引き受けたのが、戦時中一貫して義兄を支え続けた山本長治でした。


- 戦後の学園を支え続けて
-
 山本長治は山口県光市の農家に生まれました。親兄弟の努力にも支えられて広島高等師範学校(のち広島文理科大学に昇格)に進学、たまたま在学中の昭和九年に、当時精力的にキリスト教の伝道活動を行っていた物理学者、佐藤定吉博士の講演会に出席したことがきっかけで、博士に随行していた奈良育英高女教諭、三谷久男と出会うことになります。
山本長治は山口県光市の農家に生まれました。親兄弟の努力にも支えられて広島高等師範学校(のち広島文理科大学に昇格)に進学、たまたま在学中の昭和九年に、当時精力的にキリスト教の伝道活動を行っていた物理学者、佐藤定吉博士の講演会に出席したことがきっかけで、博士に随行していた奈良育英高女教諭、三谷久男と出会うことになります。三谷は京大生の頃から熱心に博士の指導を受けており、当時校長のショウも博士から指導を受けていたことが縁となって、同年一月より教員として採用され、ショウ校長の絶大な信頼を受けていました。この三谷の誘いにより、彼は十二月に開かれた学園主催の第一回宗教教育講習会に参加するため、奈良を訪れます。この時、遠来の客として校長宅に泊めてもらう待遇を受け、直接ショウとも出会うことになりました。
この縁がもととなり、昭和十二年三月長女の藤井佐和子と結婚。当時彼は宮崎師範学校の数学科教員であったので、新家庭は宮崎の地でスタートしました。ところが学園は長男の隆一が召集を受けたこともあり、その行く末を懸念したショウから、奈良の学校に転勤するよう強く奨められ、結局翌十三年九月から奈良中学に転勤することになったのです。
その後、前章の内容の通り、昭和十七年ショウ亡き後急遽育英に転勤、隆一が召集中のためにすぐさま校長事務取扱いの重責を担うことになります。隆一が学園に戻り、再度召集を受ける二十年三月までの間は、理事長・校長の隆一を支え、急速に戦時下の様相を強める状況での学校運営に努力しました。そして隆一亡き後、学園を担う決意をするのです。
 彼は終戦間もない混乱のさなか、理事会の決定により理事長・校長に就任、二十二年には藤井家の家督を相続して改姓、戦後の長きにわたり、現在に至る学園の姿を築き上げていくことになりました。
彼は終戦間もない混乱のさなか、理事会の決定により理事長・校長に就任、二十二年には藤井家の家督を相続して改姓、戦後の長きにわたり、現在に至る学園の姿を築き上げていくことになりました。彼は昭和二十一年に三谷久男を副校長として呼び戻し、創立三十周年を迎えたその年、創立者の理念と建学の精神を土台とした「育英の教育方針」を策定しました。原田美実氏の助言に基く『育英誓願』をその中軸に据え、凡ての他者への敬愛の念をもとに、学園全体で常に完全を目指す、理想の人間教育の確立を誓いました。そして学制改革の折、学園の将来を熟慮して男女共学化を決意、二十二年にスタートした新制「奈良育英中学校」は、学園初めての男子生徒を迎え入れます。そして翌年、「奈良育英高等学校」を新設、高等女学校がここに編入され、大正時代からの長い歴史に終止符を打つことになりました。
昭和二十六年、学園を私立学校法に基く学校法人とし、同時に総合学園の構想により、二十八年に「奈良育英幼稚園」を、三十一年には「奈良育英小学校」を設立、幼稚園からの一貫教育を実現する形を整えました。さらに五十八年には女子教育の伝統をふまえつつ、新たな時代を担う女性の育成を目指して「育英西中学校・育英西高等学校」を新設、学園の更なる充実を図り、その経営を長男宣夫に委ねたのでした。
その後、百一歳の長寿を全うし、平成二十三年一月三十日逝去。戦後の学園を支え続けた藤井長治の温厚篤実な人柄は、今も卒業生を始め多くの人々に慕われており、その功績は、学園の歴史が続く限り語り継がれていくことでしょう。
完(文責 和田 融)